行政手続きの多くで使われる戸籍に、いよいよ「フリガナ」が登録される時代となりました。
しかしこの制度、実は“今だけ”特別なルールが存在します。
将来的には家庭裁判所の許可が必要な「名前の読み方変更」も、今ならどんな読み方でも役所で変更できる可能性があるのです。
読み方の届出は法務省上は「訂正」形式ですが、実質的には「フリガナの変更」を公的に確定させる機会です。
「読み方を変えたいけど、家庭裁判所での手続きはしたくない」
そんな人にとって、この1年間はまさに最後のチャンスです。
この記事では、なぜ今だけ変更できるのか、どんな条件を満たせばいいのかをわかりやすく解説します。
希望の読み方へ変更ができる!役所でできる期限
読み方の変更には期限があります。
2025年5月26日から2026年5月25日までの1年間です。
家庭裁判所を通さずに戸籍のフリガナ(読み方)を変更できる特別期間です。
これは「改正戸籍法(戸籍制度)」の開始前に設けられた“経過措置(猶予期間)”で、役所だけの手続きで読み方へ訂正・登録できます。
この制度の趣旨は、「既に社会で使われている読み方を確認・反映すること」にあります。
単にイメージを変えたい目的での改名や、全く新しい読み方の登録は原則として対象外です。
ただし重要なのは、“期限までの間は、一般的な読み方でなくても条件を満たせば読み方の変更が認められる”という点です。
後述している役所で手続きが完了する、基本的なフリガナ変更の条件の例外のようなケースです。
どんな読み方にせよ、現在の戸籍の名前と違う読み方を戸籍にフリガナ登録したい方は、家庭裁判所の許可なく変更できる条件や注意点を確認しておきましょう。
戸籍にフリガナが登録される新制度とは?
2025年5月26日から始まった改正戸籍法は、全国の戸籍に正式な読み仮名を記載する仕組みです。
行政のデジタル化を進める目的で、住民票やマイナンバー情報などと一体化して管理されるようになります。
今までは戸籍に「名前の読み方(フリガナ)」は書かれていませんでした。
そのため、役所や学校で読み間違いが起こったり、書類の統一が難しいという問題がありました。
この制度によって、戸籍名の読み方が全国的に統一されることになります。
2025年5月26日から2026年5月25日までの経過措置期間に限り、戸籍に登録されるフリガナを本人申告で決めることができます。
最初に登録する“読み方”を確定する前段階のため、家庭裁判所の許可を得ずに役所で直接変更できるということです。
期限を過ぎるとフリガナも戸籍情報の一部として固定され、役所での手続きができません。
今は、読み方変更(訂正)の手続き上も心理的にもハードルが最も低いタイミングです。
家庭裁判所不要!役所で読み方を変更できる条件
家庭裁判所の手続きを経ずに、役所(市区町村)で戸籍の読み方を変更できるのは、経過措置の期間中に一定の条件を満たす場合に限られます。
読み方変更が認められやすい条件
以下のようなケースでは、役所で比較的スムーズに受理される可能性があります。
- 漢字の読み方として合理的な根拠がある(音読み・訓読み・慣用読みなど)
- 学校・職場・銀行・保険・住民票などでその読み方を一貫して使用している
- 現実に使っている読み方を反映させたい場合
このように「社会で通用している読み方」であることがポイントです。
法務省や自治体も、“現実の使用実態に即した訂正”であれば認める方向を示しています。
また、名前の“印象を変えたい”というような改名希望であっても、社会的に読み方が通用していれば変更可能です。
許可される具体例
| 分類 | 例 | 備考 |
|---|---|---|
| 音訓・慣用 | 「翔(しょう・かける)」など | 漢字の音をベースにしており、一部の音を省略したり、置き字として解釈したりする読み方である |
| 読みの省略 | 「桜良(サラ)」「彩夢(ユメ)」など | 漢字の音をベースにしており、一部の音を省略したり、置き字として解釈したりする読み方である |
| 読みの省略 | 「大和(やまと)」「弥生(やよい)」など | 熟語として一般的な読み方 |
| 長音・促音 | 「太郎(ターロー)」「一歩(いっぽ)」など | 読み方が漢字の音訓に由来していれば日常会話で行っている発音上の長音や促音(詰まる音)は許容される |
これらに該当すれば、役所(市区町村)の判断で比較的スムーズに受理されるでしょう。
却下されやすいケース
- 全く新しい読み方に変えたい
- 芸名・ニックネームを戸籍に入れたい
- 使用実績がほとんどない
役所に届け出たフリガナが認められるかどうかは、法務省の定める「一般的に認められているもの」という基準にかかっています。
戸籍に登録できる読み仮名は、基本的に漢字の字面から判断できる読み方や、社会的に慣習として定着している読み方に限定されます。
却下される具体例
| 分類 | 例 | 備考 |
|---|---|---|
| 漢字の音訓や意味と無関係 | 「翔(りく)「太郎(ジョージ)」など | 漢字の音や意味と関連性がなく造語のため |
| 漢字の意味と正反対 | 「高(ひくし)」「大(しょう)」など | 漢字本来の意味を著しく損なう読み方 |
表のような読み方は、経過措置中であっても受理されないため注意が必要です。
使用実績がカギ!読み方が変更できる証明書類
条件にあるように、一般的な読み方なら誰でも変更・訂正できます。
ただし、前述した却下されるケース(表にある読み方)でも、普段からその読み方で生活している証拠があれば、役所でどんな読み方でも変更が認められる可能性があります。
政府広報でも次のように明記されています。
「読み方が氏名として一般的に認められていない場合でも、実際に使用されていることを証明する書面を提出すれば、市区町村長が受理できる」
出典:政府広報オンライン『戸籍の氏名にフリガナが登録されます』令和8年5月25日までの猶予期間に関する案内
形式上は「訂正」ですが、実際には社会生活で通用している読み方なら、一般的な読み方でなくてもその読み方への変更が受け入れられる可能性があるのです。
却下を回避する「使用実績」の証明書類
この特例期間(2025年5月26日〜2026年5月25日)は、使用実績の有無が最大のポイントとなります。
たとえば「太郎(たろう)」を「やすし」や「たかし」と読むようなケースでも、その読み方で長期間社会生活を送っていたことを示せれば、届出が受理される可能性があります。
これは、その読み仮名が社会で定着しており、今後も混乱を生じさせないことを確認するための仕組みです。
使用実績を証明できる書類の例
- 運転免許証・マイナンバーカード
公的な本人確認書類におけるフリガナ。最も有力な証拠。 希望する読み方と一致しているか確認。 - 健康保険証・年金手帳
会保障制度で継続使用されている読み方。使用期間が長いほど有効。 - 住民票・住民票記載事項証明書
役所に登録された正式なフリガナ。過去に変更履歴が残っている場合に特に有効。 - 卒業証明書・在学証明書
教育機関でのフリガナ。義務教育期間など長期間の使用が強い根拠になる。 - 銀行通帳・キャッシュカード
金融機関で登録された読み方。届出前にフリガナが記載されているか要確認。 - パスポート
国際的な公的書類。希望する読み方が使われていれば非常に有力。
法務省が例示する『通用していることを証する書面』は上記の通りです
これらの使用実績を提出することで、「この読み方で社会生活を送ってきた」という事実を強く裏付けられます。
実際の窓口で変更手続きする注意点
期限を厳守
この期限を1日でも過ぎると、原則として家庭裁判所の許可(裁判手続き)が必要となり、手続きの難易度と期間が格段に上がります。
自治体によって判断基準が微妙に異なる
法務省の条件を満たしていても、最終的な役所の審査で却下される可能性はゼロではありません。
使用実績の証明書類を複数用意するなどの対策が必要です。
役所での読み方の変更・訂正は一度きり
猶予期間中に届け出たフリガナは、再度、役所で手続きをして変更することはできません。
その後の変更には家庭裁判所の許可が必須になります。
通知書と異なるフリガナを役所で訂正・変更する際は、本当にその読み方で一生過ごす覚悟があるか、よく考えてくださいね。
家庭裁判所不要!戸籍の読み方の変更条件のまとめ
経過措置期間に限り、使用実績という条件を満たせば、一般的に認められにくい読み方でも、家庭裁判所の許可なしに役所への届け出だけで登録できる可能性があります。
今のうちに手続きをすれば、これまで戸籍上と異なる読み方で生活してきた人でも、自分の本来の読み方を正式に登録することができるということです。
しかし、手続きは一回限りで、一度届け出るとその後の変更は家庭裁判所の許可が必要となります。
読み方の訂正や変更の許可は、役所によって判断が異なる可能性もあります。
戸籍のフリガナを変えるなら、証明書類を複数準備し、期限内に悔いのないよう手続きを進めましょう。
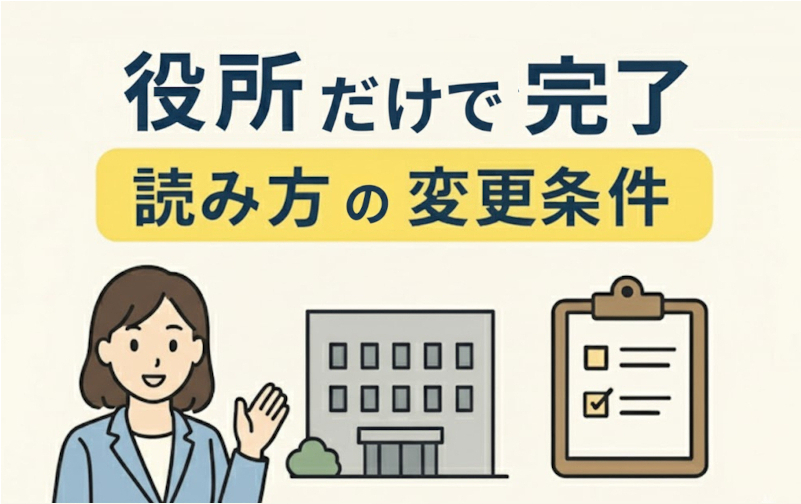

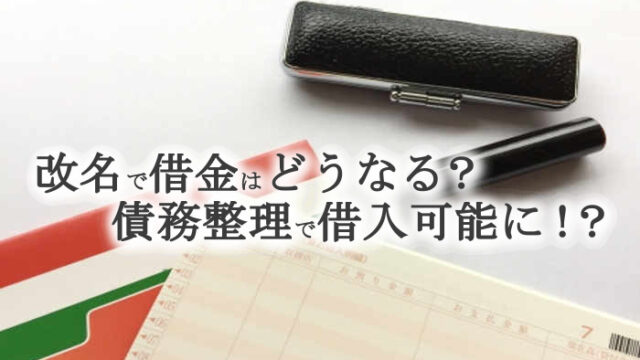
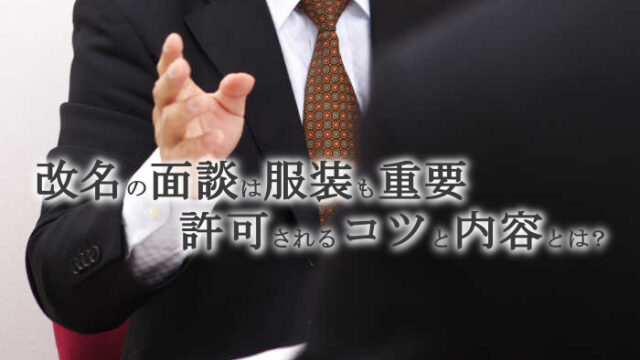
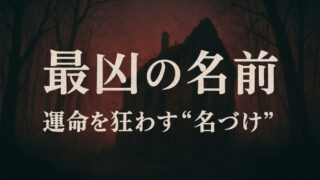
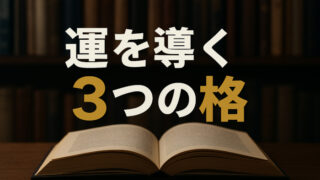
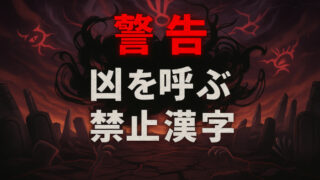

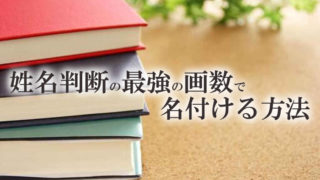
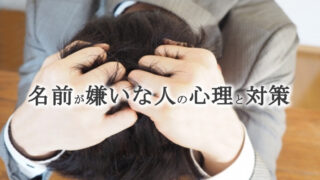
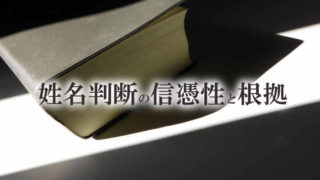

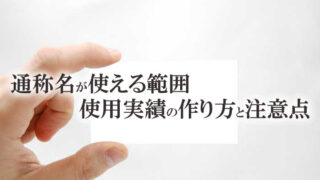
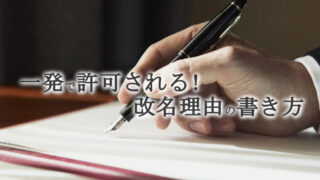
はじめまして!
名前のフリガナ変更について問い合わせだけしてみようと思い、県内の管轄外の役所に問い合わせたら「え?フリガナですか?んー、、、出来ませんって事で良いですか?」と、あまりよく分かっていない様子でした。
なら自分の管轄する役所はどうなのかと思い管轄の役所に問い合わせたら、なんと「出来る」と言われました!
来年頃から名前のフリガナ変更も難しくなるみたいなので明日変えちゃいます!笑
持ち物は身分証とフリガナ表記されている役所から渡された証明書などみたいですね。
本来は名前を変えたいんですが難しいみたいなので、、、でもフリガナだけ変えられて良かった。
数年後これを名前変更に繋げたいですね!
フリガナを変更できるようでよかったです!
今後は変更が難しくなると思われるので、今のうちに変更するのがいいです。
フリガナは出生時に届けているのですね。しかし、それが、戸籍には反映されているのか、住民票には反映されているのか、国民側ではよくわからないですけど、住民票基本登録台帳で登録されている場合があるようです(自治体による)。この住民票基本登録台帳は、住民票に関するものだと思いますから、戸籍の方が依然として、フリガナは存在しないのかな、と理解しています。詳しく言うと、このような状態が、2023年度までの状況だったと理解しているのです。
しかし、2024年度からは、違うのですね。戸籍の方も、住民票の方も、フリガナが付くのですね。
仮に、出生届が戦前だったら、フリガナは届けていたのだろうか、と思いました。もしも、戦前の出生届にもフリガナ欄があったのならば、昔の仮名で、「よしゑ」とか、『ゐ』『ゑ』を届けていた人もいると思いました。
これらのひとは、今回の2024年の法令で、「よしえ」になってしまうのか、「よしゑ」なのか、宙ぶらりんな状態ですね。確かめに行かないと、曖昧な気持ちのままです。
また、「自分としては、こっちにしてほしいのだ」という意思のある場合もありますね。
2024年に政府は改正戸籍法を2025年5月26日に施行を決定しています。読み仮名を「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」と定めていますが、本人の意思を尊重する可能性もあります。正確な情報を得るには、2025年5月26日以降に本籍地の市区町村で確認するしかありません。
有難うございました。
住民票基本台帳において、川原(かははら)さんなど苗字の場合もあるかもしれません。あまりなさそうですが。他方、
古い戸籍には、役所の人が、自分の裁量で仮名を振っていて、
まったくもって、歴史的仮名遣い風の場合もあるかもしれません。それが今回、一律に、一意に決まれば、今後は混乱はなくなると思いました。
過日、私が書きました「よしゑ」は、もしかして、パスポートでは、Yoshiweになってるかもしれず、尊重される可能性もゼロではないなと思いました。なお、「文緒(ふみを)」などは、
そのまま認められる可能性が高いと思いました。
(普段、「ふみおちゃん」と呼んでおり、『お』か『を』など、意識してはいないのが通例かと思います。)
確かに「川原(かははら)」さんのような珍しい読み方や、昔の戸籍の歴史的な仮名遣いなど、色々なケースがありそうですね。
今回の改正で、こういった多様な表記が整理されるのは良いことだと思います。「よしゑ」さんや「文緒(ふみを)」さんのような例も、一般的に使われている読み方なら問題なさそうに感じます。
返信ありがとうございます。
「川原(かははら)」の『かは』は歴史的仮名遣いですし、認めてくれない可能性もありますが、ゴタゴタの混乱もあるでしょうから、認めてくれるかもしれないと思います。
『を』は現状でもきちんと存在していますけども、『ゐ』『ゑ』は認めない可能性もありますけど、やはり認めてくれるかもしれないですね。
実際に、ハガキの宛名では、『ゐ』『ゑ』は、そのまま通用していそうです。
歴史的仮名遣いや特殊な読み方の扱いは、2025年5月26日の法改正施行後に明確になるかもしれません。「川原(かははら)」や『ゐ』『ゑ』などの扱いも、本人の意思が尊重される可能性がありますね。日常使用と戸籍記載が異なる可能性もありますが、最終的には各自治体の判断になります。
有難うございます。自治体ごとの判断になるだろうというのは興味深い考察、実務家ならではの考察だと思いました。
たとえば、近衛家(勝手にお名前を出して恐縮ですが、日本で最も有名な苗字=家名=のひとつです)の場合、「このゑ」が可能かどうか、と思いました。京都人なら、近衛家の権威は御存じのところかと思います。
尤も、一族で、ある程度は、平仄を併せる動きもあるかもしれません。
戸籍は戸籍という、割り切りもあるかもしれません。明治になって作りだした、戸籍などに右往左往する価値はないかもしれません。
私のような一般庶民にとっては、戸籍に載せた「氏」をどうするかは非常に気になりますが。
近衛家のような歴史的な家名における仮名遣いや読み方の扱いは、特別なケースとして議論の余地がありそうですね。一族での統一性や伝統を重んじる動きがある一方で、現代の戸籍制度との折り合いをどうつけるかは難しい課題だと思います。一般庶民にとっても、戸籍上の氏名や読み方が生活に与える影響は大きいので、今後の具体的な運用が注目されますね。