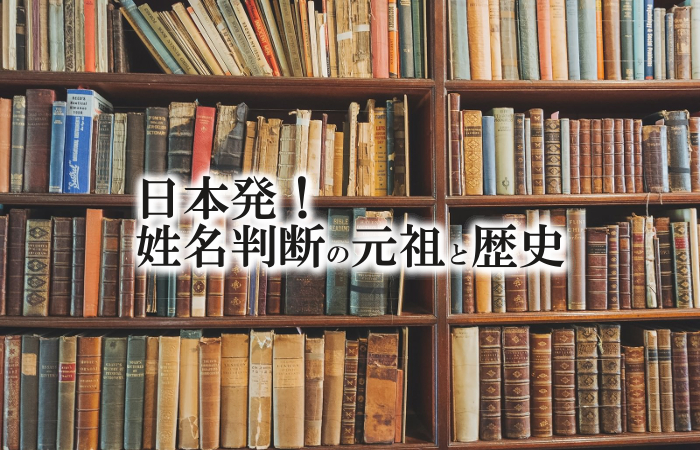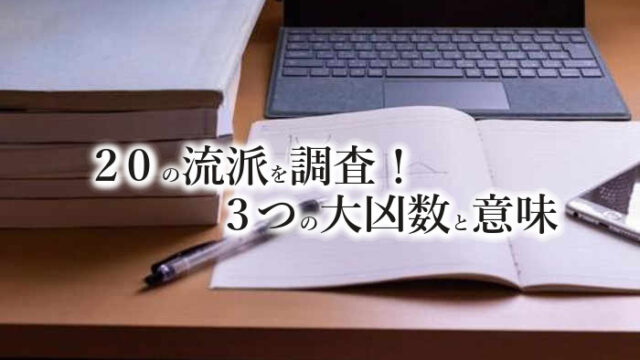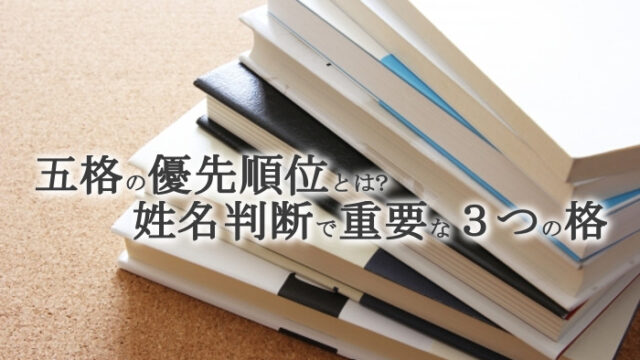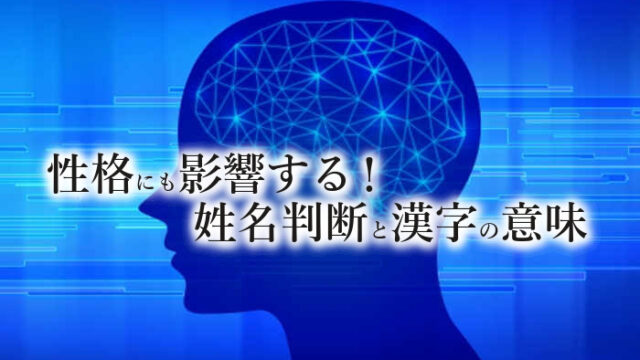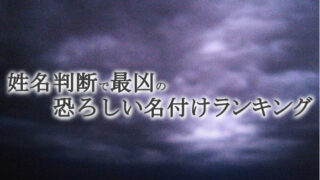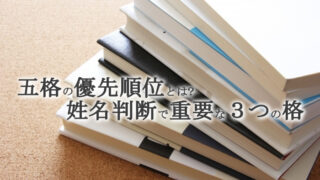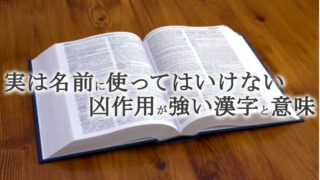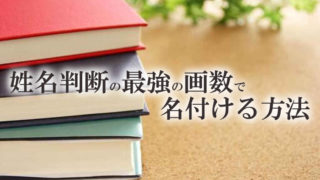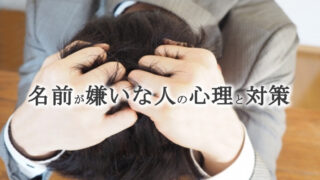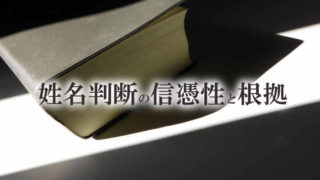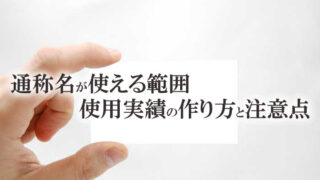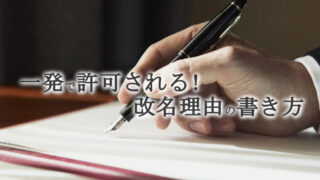姓名判断の元祖といえば熊崎式です。
今の姓名判断の源流となっていますね。
しかし、姓名判断の歴史を調べると、元祖は他にもいます。
さらに姓名判断は中国発祥と思われがちですが、実は日本が発祥です。
ここでは姓名判断の歴史や元祖などについて調べてまとめました。
ちょっとマニアックですが、姓名判断の歴史を知ることで疑問が解消されたり、納得できる答えが見つかるかもしれません。
少なくとも、歴史を知ることは姓名判断への理解が深まるのではないでしょうか。
参照元
「Amebaブログ『「姓名判断」は当たるか?』(tengkozo著)」
『日本占法大全書 2006/5/1頼富 本宏 (監修), 佐々木 宏幹 山折 哲雄 藤井 正雄-|書誌詳細|国立国会図書館オンライン』
『古今諸名家 姓名善悪論 初編 菊池准一郎(著) 出版者 天命堂 出版年月日 明26.3-国立国会図書館デジタルコレクション』
『新式姓名法 佐々木盛夫 著 出版者 哲明堂 出版年月日明36.8-国立国会図書館デジタルコレクション』
『姓名学の誕生 -大衆新聞の登場と読むことの想像力を中心に- 京都文教大学人間学部研究報告 第10集,87-113頁 (単著) 2008/03』
画数による姓名判断は日本発祥
姓名判断は画数によって吉凶を占います。
漢字のルーツである中国の陰陽五行を使って占う部分もあり、姓名判断は中国から伝わったと言われます。
しかし、当時の中国では字画による姓名判断はなく、字義や字形による姓名判断に似たものがありました。
姓名判断の歴史を見ると、どうやら名前の画数を使って吉凶を占う方法は、日本で生まれた日本式のようです。
今の姓名判断の元祖といえば熊崎健翁氏です。
しかし、2006年5月出版の書籍『「日本占法大全書」頼富 本宏(監修), 佐々木 宏幹 山折 哲雄 藤井 正雄』によると、熊崎氏の姓名判断は1940年代に留学生によって台湾に伝えられたそうです。
姓名判断は中国から伝わったと勘違いしてしまいそうですが、画数を使った姓名判断は実は日本が発祥(起源)でした。
画数の姓名判断の起源は梅花心易?
名前の画数を合計して吉凶を占う今の姓名判断の手法は明治に登場しましたが、日本では画数で占う方法自体は江戸時代にありました。
それが梅花心易(ばいかしんえき)です。
梅花心易は中国の宋代(紀元960年~1127年)に開発され、日本では江戸時代後期から盛んに研究されてきました。
梅花心易はこの世に存在する全てが対象となり、占おうとした時の状況や目に入ったものの運勢や吉凶を占います。
名前の画数も占うことができます。
易の一種の占いですが、「筮竹(ぜいちく)」という竹の棒などの道具を使用しません。
梅花心易はあらゆる事柄を数に置き換えて占うため、姓名判断の場合は名前の画数を八掛(はっけ)に落とし込んで活用します。
名前の画数を卦を構成する八掛の相克関係(五行)から吉凶を占うのですが、たとえば、梅花心易は数が9以上の数字は8で割り(払う)ます。
17画なら8で割ると1、1の易数は乾となり、同じように他の画数も計算して吉凶を見ます。
名前の画数の合計で吉凶を占う手法を使った手法が出てから、易の占いは低迷しそれができる占い師はごく少数です。
画数ではなく字音による反切の歴史
姓名判断として画数を使うものではないですが、古くから用いられてきた方法として「反切法(はんせつほう)」があります。
「反切」は「韻鏡(いんきょう)」という、10世紀ころにできた中国語の発音を示す一覧表(等韻図)です。
反切法とは、漢字の音を子音と母音に分解して表す方法です。
日本には名乗反切というのがあり、漢字の読み方から占う姓名判断の一つで、江戸時代に流行りました。
ちなみに、あの信長という名前は中国の反切法を用いたそうな。
日本人としてはじめて「音韻」を用いたのは弘法大師(空海)です。
弘法大師は、真言密教の教学の一環として悉曇学(しったんがく)を学びました。
悉曇学は日本語の音韻研究に影響を与え、アイウエオは悉曇学の母音の順です。
画数(霊数)での姓名判断の元祖は熊崎氏?
姓名判断はいろんな元祖がいます。
どのようにして元祖が生まれ、今の画数で吉凶を占う姓名判断になったのか、そのあたりの歴史や流れをみていきましょう。
本当の元祖!?明治26年菊池准(準)一郎の姓名判断
現在の姓名判断の元祖で有名な熊崎氏ですが、明治26年(1893年)には画数で占う今のような姓名判断が出ています。
熊崎氏よりも前に姓名判断を作った元祖として、菊池准(準)一郎氏がいます。
1893年に出版した『菊池准(準)一郎(著)「古今諸名家 姓名善悪論 初編」(出版者天命堂)』があり、これは画数を使った占いの最も古いであろう書籍です。
菊池准(準)一郎氏が姓名判断を最初に作った元祖なのかは不明ですが、初編の本には「どのようにして画数と吉凶を関連付けたのか」その解説があります。
たとえば書籍を読むと、人相学で鼻は財帛宮といい生涯の財運がわかる部分で、これを活用していることがわかります。
財帛(宮)は41歳~50歳で第5運を表すのですが、そういった数字が画数に関連しているのかもしれません。
姓名判断は1画から81画までで吉凶があり、これを元に鑑定士は姓名判断の統計を取ったり運勢を読み解きます。
しかし、「そもそもなぜその画数が大吉や凶なのか」という解説をしている書籍も姓名判断の占い師もいません。
そういった根拠を明確に答えられる人は、姓名判断を作った人以外いないでしょう。
姓名判断の歴史を調べると、菊池氏は名前の画数で吉凶を見るという、姓名判断の原型を作った人物かもしれません。
姓名判断の元祖は他にもいる(海老名氏・佐々木氏)
明治26年(1893年)には菊池准(準)一郎氏の画数を使った姓名判断がありますが、他にも元祖的な人物がいます。
その一部として、佐々木盛夫氏と海老名復一郎氏をご紹介します。
佐々木盛夫氏は、明治34年に報知新聞に姓名判断の記事を掲載、これは姓名判断が新聞に掲載された最初の事例です。
また、佐々木氏は、明治36年8月に姓名判断の書籍『「新式姓名法」 佐々木盛夫(著) 出版者 哲明堂』を出版しています。
他の姓名判断の元祖として挙げられるのは、海老名復一郎氏がいます。
海老名氏は、大正3年に姓名判断の書籍『「姓名判断 新秘術 3版」海老名復一郎(著) 出版者 海老名天口堂』を出版しています。
これは3版なので、初刊は大正3年以前かもしれません。
現在の姓名判断の元祖.熊崎健翁氏
姓名判断の元祖というと、その歴史上で欠かせない人物が熊崎健翁氏です。
元祖といえば有名な方です。
姓名判断の基本型の多くは明治や大正にありましたが、熊崎氏は現在の主流な姓名判断の基本型を作った方です。
歴史を見るとこれまでの姓名判断には、
- 音韻+五行(五気とは別)
- 名前の発音に五行と意味付け
- 画数は康煕字典に従う
- 漢数字は実数(五は5画)
などがありますが、熊崎式の特徴は、
- 5格にした
(人格と外格を追加) - 天地三才
(天格と人格・人格と地格の五行の吉凶) - 一字姓と一字名は1画を足す
(総格には加えない)
といった技法です。
現在は熊崎氏の技法をもとにした多くの流派があります。
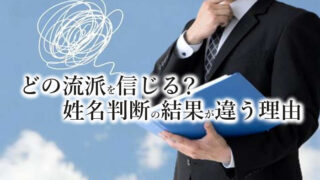
佐々木氏が報知新聞に連載を書いたこともあり、明治末期から大正初期に姓名判断の第一次ブームがありました。
熊崎氏の登場で戦前に爆発的な流行を見せ、さらに戦後のベビーブームもあって姓名判断は全国的に広まっていきました。
当時の熊崎氏は新聞記者でしたが、昭和3年に運命学の鑑定所「五聖閣」を設立し、翌年に熊崎式姓名学の発表で一世を風靡しています。
今も熊崎氏の手法が受け継がれ、その影響力の大きさがよくわかりますね。
現在の姓名判断の技法は熊崎式がベース
姓名判断の歴史を見ると、
- 梅花心易
- 5格の画数
- 三才(天人地)の五行の相互関係
- 天地同格や同数
- 4運(人地外総)に社会運や家庭運を追加
- 音韻
他にも方法がありますが、これらのうち5格(天格・人格・地格・外格・総格)は、どの姓名判断(流派)でも引き継がれるくらい姓名判断の基本となっています。
そして人格・地格・外格・総格の4運で吉凶を占うのが現在の姓名判断の主流です。
熊崎式である5格(4運)はどの流派も共通して扱っていますが、それ以外の技法は三才や音韻を扱わなかったり逆に重視したりと、流派によって扱い変わります。
他にも、統計重視で暗示といったスピリチュアルは考慮しない流派や、旧字体・常用漢字・戸籍・康煕字典など、どの漢字で占うのか流派で違います。
姓名判断は運命学であるため、統計や数字を否定する流派もあります。
ただどの流派も5格4運が共通しているので、多くは熊崎式に独自の技法をあみ出しているという具合です。
姓名判断は流派があまたの数あります。
当たっていようが外れていようが、納得できる鑑定結果ならそれがあなたにとって合っているということです。
姓名判断を活用するなら、いろんな先生に鑑定を依頼するといいです。
特にネット鑑定は格安で受けられることも多いのでオススメ!
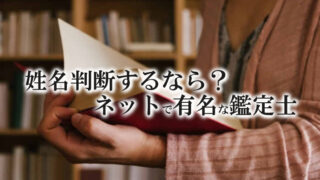
姓名鑑定を依頼してその鑑定士があなたに合っているのか、地道に探しましょう。
日本発祥!姓名判断の元祖と歴史のまとめ
姓名判断の元祖とされる人物は歴史を調べると何名かいて、姓名判断は実は日本発祥だったことがわかりました。
画数の吉凶の根拠などは明確ではないですが少しは知ることができました。
姓名判断で何か気になることがあれば、歴史を調べるとヒントが得られるかもしれませんね。